タイカ・ワイティティが送った少年へのエール 『ジョジョ・ラビット』の音楽
マガジン「映画のはなし シネピック」では、映画に造詣の深い書き手による深掘りコラムをお届け。今回は、『ジョジョ・ラビット』で使用されている印象的な音楽に注目。映画や音楽をメインに文筆家として活躍する、長谷川町蔵さんにコラムを寄せていただきました。
文=長谷川町蔵 @machizo3000
第二次世界大戦下のドイツの田舎町。少年ジョジョ(ローマン・グリフィン・デイヴィス)はこれからナチス傘下の青少年団体ヒトラーユーゲントの夏合宿に出かけるところだ。
「僕にはムリかも」
躊躇する彼に、ナチス・ドイツ総統アドルフ・ヒトラーその人がぬっと励ます(もちろん彼はジョジョの空想の産物だ)。
「大丈夫。お前のナチスへの忠誠心はピカイチだ!」
意を決したジョジョが玄関から飛び出すと、耳慣れたロックチューンが流れ出す。ザ・ビートルズ初期の名曲「抱きしめたい」のドイツ語版だ。曲に合わせてインサートされるヒトラーに熱狂する当時のドイツ人たちが、まるでビートルズに熱狂するビートルマニアのように見えるのが面白い。
『マイティ・ソー バトルロイヤル』(’17)で名を上げたニュージーランド出身のタイカ・ワイティティが監督、製作、脚本、ヒトラー役の4役を務めた『ジョジョ・ラビット』(’19)は、そんな時代設定を無視したシュールなシーンで幕を開ける。
ポール・マッカートニーは、ナチスを描いた映画に曲を使いたいと依頼が来た当初は躊躇したそうだが、映画のコンセプトを説明されて快諾したという。本作はマオリ人とユダヤ人のハーフであるワイティティによる強烈なアンチ人種差別コメディなのだ。
冒頭シーンはあくまでナチスに洗脳されたジョジョの脳内の光景にすぎず、まだ10歳の彼にとってヒトラーユーゲントは林間学校と大差がない。訓練シーンに流れるのが、トム・ウェイツが子ども視点で歌った1992年の楽曲「大人になんかなるものか」であることがそのことを象徴している。しかしジョジョの洗脳は、屋根裏部屋に隠れ住んでいたユダヤ人少女エルサ(トーマシン・マッケンジー)と出会うことで解け始める。
エルサを匿っていたジョジョの母ロージー(スカーレット・ヨハンソン)は、戦時中にもかかわらず着飾ってワインを飲んでいるのだが、これには理由がある。ナチス以前のドイツは世界で最もリベラルな国だった。彼女がレコードでジャズ(エラ・フィッツジェラルド「ディプシー・ドゥードゥル」)やラテン(レクオーナ・キューバン・ボーイズ「タブー」)を聴いているのも、当時の人気曲だからである。ロージーはライフスタイルすべてでナチスに反抗しているのだ。
そんな気骨ある母に対するジョジョの想いを、ロカビリー・シンガー、ロイ・オービソンが1962年に発表したスウィートなバラード「ママ」が代弁している。
だが物語後半、連合軍の攻撃は激しさを増していき、「生きてる者はみんな死ぬ」と連呼するサイケ・ポップバンド、ラヴによる1974年の楽曲「エヴリバディズ・ガッタ・リヴ」に乗せてジョジョの町は廃墟と化していく。
そして映画は急転直下クライマックスを迎えるのだが、このシーンをこれ以上ないくらい盛り上げてくれるのが、故デヴィッド・ボウイの代表曲「ヒーローズ」ドイツ語版だ。
第二次大戦後のドイツは、社会主義体制と資本主義体制二国に東西分裂して首都ベルリンも壁で東西に分断された。1977年発表の「ヒーローズ」は、当時西ベルリンに住んでいたボウイが、壁のそばでわざといちゃついて東ドイツ軍兵士を挑発する西ベルリンのカップルを見て感激したことから生まれたという。
1987年、西ベルリンでライブを行ったボウイは、スピーカーを壁側にも向けて歌声を聴かせた。熱狂する東ベルリン市民に対して軍や警察は全く手出しできなかった。この経験が彼らに勇気を与えた。2年後、東ドイツ政府が西ベルリンへの通行規制緩和を発表すると、東ベルリン市民は壁を突破するだけでなく壁そのものを破壊。1990年にドイツは東西統一を果たしたのだった。
もしかするとジョジョはこれから厳しい人生を送るのかもしれない。でもいつかは輝かしい未来がやってくる。ワイティティは「ヒーローズ」を通じて、ジョジョにエールを送っているのだ。
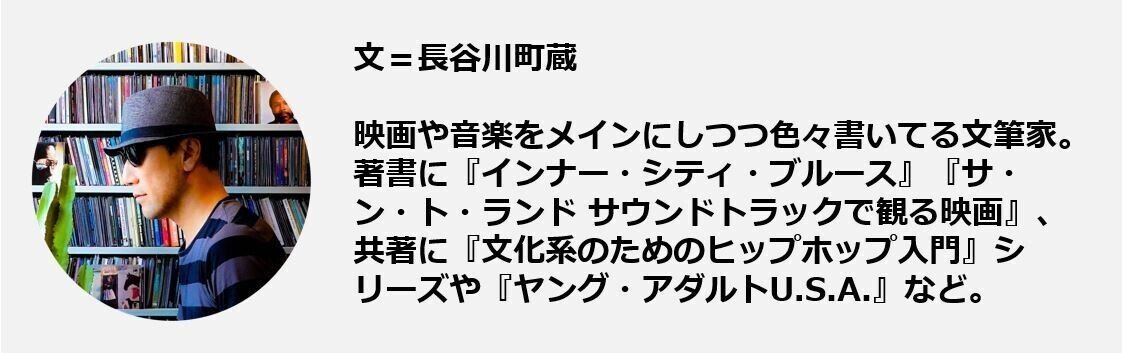
▼作品詳細はこちら

