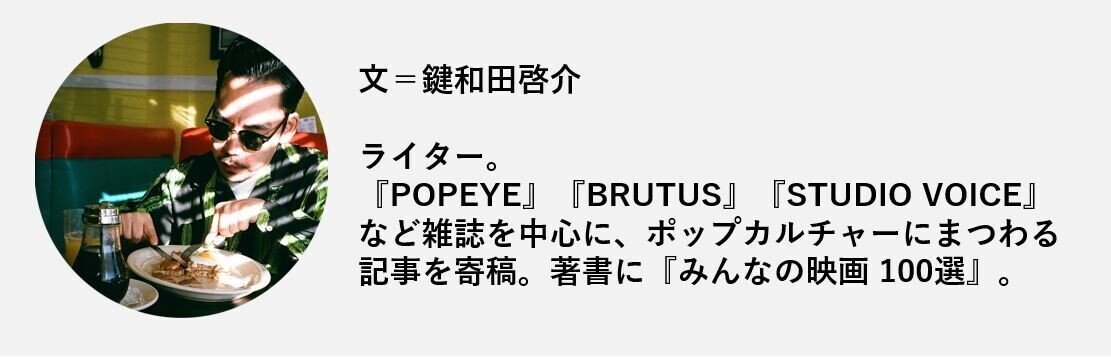気鋭の映画スタジオ「A24」の、1990年代と今をつなぐ“再生計画”
マガジン「映画のはなし シネピック」では、映画に造詣の深い書き手による深掘りコラムをお届け。今回は気鋭のスタジオ、「A24」が製作や米国配給を手掛けた作品群の魅力を、メディアへの“秘密主義”で知られる同社への直接取材に関わったライターの鍵和田啓介さんに分析してもらいました。
文=鍵和田啓介 @kaggy_pop
「A24」の作品を観ていると、1990年代後半から2000年代前半にかけて、ストリートファッションをはじめとするユースカルチャーと連動しながら、ヒップな若者たちを魅了したインディーズ映画のバイブスを思い出す。スケーターたちの日常とHIVの脅威を描き、ファッションを含むスケートカルチャーを世に知らしめた青春映画『KIDS/キッズ』(’95)を筆頭とする、日本では“ミニシアター系”と呼ばれるタイプの作品群だ(以後、便宜的に“90年代映画”と呼ぶ)。
2012年に創設された映画スタジオ「A24」は、そのバイブスの現代におけるリブート(=再生計画)をもくろんでいるように思われる。具体的な活動を開始した2013年、同社がハーモニー・コリンの『スプリング・ブレイカーズ』(’12)とソフィア・コッポラの『ブリングリング』(’13)を米国で配給していることからも、それは伝わってくる。『KIDS/キッズ』で脚本を手掛けたコリンと、ストリートブランドに携わった後、監督デビュー作『ヴァージン・スーサイズ』(’99)で一躍ガーリーカルチャーのカリスマとなったソフィア・コッポラこそ、“90年代映画”のムーブメントを率いた監督なのだから。
同社の作品に青春映画が多いのは、そうしたもくろみ故だろう。もちろん、現代においてリブートする上では、アップデートも必要不可欠だ。例えば、第89回アカデミー賞で作品賞を含む3部門を受賞した『ムーンライト』(’16)は、メインストリームの映画で肯定的に描かれることがほぼなかったLGBTQの黒人少年を主人公に据えた点が、革新的だったといえる。他にも、1970年代を舞台にフェミニズムを学びながら成長する少年の日常をつづる『20センチュリー・ウーマン』(’16)、SNS世代ならではの少女の葛藤を活写した『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』(’18)、スケーター青年を通してサンフランシスコにおけるジェントリフィケーション(再開発)の是非を問う『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』(’19)、あるいはドラマではあるが、そうしたテーマのほとんどを盛り込んだ「ユーフォリア/EUPHORIA」(‘19~)など、「A24」作品には現代的な題材を扱った青春映画が多い。
もちろん、こうした題材自体は「A24」以外の映画スタジオも扱ってはいる。“90年代映画”バイブスは、それをクールな映像表現で魅せる点に表れる。クールさの内実は監督によって異なるものの、『ムーンライト』、「ユーフォリア/EUPHORIA」、『グッド・タイム』(’17)、『WAVES/ウェイブス』(’19)で、ネオンサインの極彩色が印象的に用いられていることは指摘しておきたい。まるでウォン・カーウァイ作品を想起させるが、実際、『ムーンライト』のバリー・ジェンキンスや『WAVES/ウェイブス』のトレイ・エドワード・シュルツは、カーウァイからの影響を告白している。香港映画ではあるものの、彼もまた1990年代のユースのカリスマ的監督だけに、かなり興味深い。監督たちもまた、“90年代映画”をリブートしようという意志があるのだろうか。
また、“90年代映画”において、ファッションとの連動が重要だったのは冒頭に示した通りだが、その点で際立っているのが、サフディ兄弟の一連の監督作品だ。とりわけ注目したいのは、NYの宝石商を主人公に据えた悲喜劇『アンカット・ダイヤモンド』(’19)だろう。前作『グッド・タイム』に続いて衣装を手掛けたのは、ファッションギークなユースから絶大な支持を仰ぐ、ファッション・ディレクターのモルデカイ・ルビンシュタインとコスチューム・デザイナーのミヤコ・ベリッツィ。2人が生み出した主人公のアイコニックなルックは、海外のファッション誌から軒並み絶賛されたが、本作とファッションのつながりは作品内にとどまらず、さまざまな展開を見せた。例えば、同作とLAのストリートブランド「Online Ceramics」のコラボTシャツは、「A24」のサイトで販売された瞬間ソールドアウトになった。
このようにグッズ展開に力を入れているのも、「A24」の特徴といえる。同社のサイトをのぞけば一目瞭然だが、社名ロゴをあしらったアパレルから各作品をモチーフにしたおもちゃなど、ここまでグッズを制作している映画スタジオは他にない。中でも興味深いのは、作品がリリースされるのと同じタイミングで、多くの監督たちにZINE(紙をホチキスで留めただけのDIY雑誌)を作らせていること。ZINEは1990年代のユースカルチャーの中において、広がっていったメディアだからだ。
そんな「A24」による“90年代映画”再生計画の真骨頂といえるのが、そのものズバリなタイトルを冠した『mid90s ミッドナインティーズ』(’18)に他ならない。実際、本作では、今まで書いてきたエッセンスがすべて凝縮され、結晶化している。監督を務めたのは俳優のジョナ・ヒルであり、本作には彼自身の経験が反映されているという。
舞台は1990年代のLA。母と兄の3人で暮らす、13歳のスティーヴィー(サニー・スリッチ)が主人公だ。兄にいじめられてばかりの退屈な日々を過ごしていた彼が、同世代のスケーター少年たちと出会い、毎日のように遊ぶ中で、かけがえのない友情を知る。『mid90s ミッドナインティーズ』がみずみずしいタッチで描くのは、そんな青春物語だ。
スティーヴィーの仲間たちは、ナケル・スミス、オーラン・プレナット、ジオ・ガリシアら『KIDS/キッズ』と同じく実際のプロスケーターが演じている。また、ハーモニー・コリンがスティーヴィーの母のボーイフレンド役でカメオ出演しているのも見逃せない。さらにヒルはこの脚本をスパイク・ジョーンズに相談しながら書き上げたそうだが、スパイクもまた“90年代映画”の重要人物だ。そんな形で、本作は新旧のユースカルチャーとの紐帯を示している。
ファッションについても、事情は同じ。スケートボードブランドの「GIRL」をはじめ、登場人物たちは1990年代当時のストリートブランドをまとっている。にもかかわらず、どこか今っぽさも感じられるのは、そうしたブランドが再注目されていると同時に、「アディダス」とのコラボスニーカーを発表するなど、ファッションアイコンの地位を確立しつつあるヒルのセンスに違いない(ちなみに、彼は前述したモルデカイ・ルビンシュタインの写真集にモデルとして登場している)。もちろん、本国公開の際にはTシャツやZINEが作られた。
物語について言えば、一見すると普遍的な青春物語のようだが、スティーヴィーが仲間たちに促されるように、どんどん悪くなっていく点に注目しよう。男たちが仲間内のノリでワルを演じ、女性や同性愛者への不届きな振る舞いを働くようになることは、近年、「トクシック・マスキュリニティ(有害な男らしさ)」と呼ばれて問題視されている。本作でそれが最もよく表れているのが、スティーヴィーが仲間のひとりから「ありがとうなんて言うな。ゲイっぽいから」と言われるシーンだろう。『mid90s ミッドナインティーズ』は、1990年代当時の記録として、そうした負の側面も美化せず描いている。そこには、前述の青春映画と同様に、現代的な問題への提起を読み取ることも可能だろう。
という具合に、本作が「A24」の“90年代映画”再生計画の集大成的な作品であることは間違いない。だとしたら、創設からちょうど10年を迎える来年以降、どのような作品を手掛けていくのだろうか。この方向性をより先鋭化させていくのか、はたまたまったく別の方向にかじを切るのか。いずれにしても、今後が楽しみな映画スタジオである。