
イラストレーター・信濃八太郎が行く 【単館映画館、あちらこちら】 〜「シネマイーラ」(静岡・浜松)〜
名画や良作を上映し続けている全国の映画館を、WOWOWシネマ「W座からの招待状」でおなじみのイラストレーター、信濃八太郎が訪問。それぞれの町と各映画館の関係や歴史を紹介する、映画ファンなら絶対に見逃せないオリジナル番組「W座を訪ねて~信濃八太郎が行く~」。noteでは、番組では伝え切れなかった想いを文と絵で綴る信濃による書き下ろしエッセイをお届けします。今回は静岡・浜松の「シネマイーラ」を訪れた時の思い出を綴ります。
文・絵=信濃八太郎
音楽の街、浜松の映画館を訪ねる
「なにが芸術だ。なんでおまえは踊ったり絵を描いたりするんだ?」
「お父さんはなんでトイレに行くんだ?」
「体が要求するからだよ」
「それと一緒だよ」
世界で最も有名なパントマイム・アーティスト、マルセル・マルソーの人生を描いた映画『沈黙のレジスタンス ~ユダヤ孤児を救った芸術家~』('20)のセリフである。
マルセル・マルソーのパフォーマンスを映像で見たことはあったけれど、第2次世界大戦中にレジスタンスに参加したこと、大勢のユダヤ人孤児たちをナチスドイツの手から逃したことなど、全く知らないことばかりだった。ひとつひとつの動きに漂う悲哀のような情感は、自身の経験から滲み出てきたものだったんだと、映画を観て理解した。
ジェシー・アイゼンバーグ演じるマルセルの素晴らしいパフォーマンスで映画は終わる。エンドロールが流れる間、先ほど来た道で目にした光景が過ぎる。
浜松駅の構内には誰でも自由に弾けるピアノやギターが置かれていて、高校生らしき制服姿の男子が気持ち良さそうに鍵盤を鳴らしていた。自分の母親くらいにも見える白髪の女性はギターを爪弾く。そんな演奏を立ち止まって笑顔で聴く人がいる。
工業都市だった浜松は、戦時中、主要工場が軍需目的に転用されたため空襲を受け、町の多くが焼けた。今、自分が感じたことを自由に表現できるこの時代の素晴らしさ、有り難さをあらためて思う。学ぶことの多い作品だった。明るく戻った館内。たくさんの人が入っていたことに気付いた。
今回訪ねるシネマイーラには番組宛てに取材リクエストをくださった方から「18歳で東映に入社してから映画一筋50年。浜松にとても面白い館主がいる」とコメントを寄せていただいた。取材は明日。お会いするのが楽しみだ。今日のうちに屋外でスケッチを進めておくことにした。
東京よりも暖かな冬の日射しが気持ち良い。一つ困ったのが、風が強くてスケッチしている紙を巻き上げてしまい、そのたびに線がぶれてしまう。これが「遠州の空っ風」というやつか。どうにかならないかとあれこれ工夫しているうちに、上半身をかがめ気味にして、肘で紙を押さえながら手首も固定して描くという妙なポーズのまま進めることになった。弁当箱を隠しながら立ち食いしているような格好だ。カメラが回るのが明日でよかった。
翌朝、約束の時間より早く集合した番組制作スタッフがそれぞれ準備をしていると、ビル上方の窓が開いて「おーい、三階だよー!」と手を振ってくださる方がいる。館主の榎本雅之さんだ。お声一つで空気が明るくなった。
三階に上がってごあいさつも済み、早速カメラが回り始めたところで「あ、電気屋さんが来ちゃった! ちょっと待ってね。悪いね、重なっちゃって!」と榎本さん。「こっちこっち!」と、長い脚立を持った電気屋さんを劇場内に案内して、再び戻ってこられる。
「電球が切れちゃってね。これで大丈夫ですので、もう一回お願いします」
少しお話ししたところで、今度は館内から大きな作業音がした。
「やっぱりちょっと待っててもらえますか!」
ひとり電球交換の作業をしている電気屋さんを榎本さんが手伝う間、しばし休憩となった。
高い天井の映画館の電球交換。当然だけれど、初めて見た。何メートルあるんだろう、あの脚立の上まで行くのはとても怖そうだ。
「普段は天井まで届く長い棒を使って自分で替えてるんだけどね、今日はソケットが切れちゃって。それで自分じゃ無理だから電気屋さんに来てもらったわけ」

榎本さんにとっての日常の風景。僕にとっては大きな気付きだった。
今までたくさんの映画館を取材してきたけれど、上映作品の編成や思い出深い映画のことなどいわゆるソフトの方ばかりに気を取られていた。しかしその裏には映画館という巨大なハードを維持するための膨大な日々の仕事がある。今日この作業に立ち会えたことがとても貴重なことのように思えた。
「なんでも自分でやってます。今日も皆さんが来る前にトイレ掃除して、椅子も除菌して、映写機のスタンバイもして試写の確認も終わって、それで今こうしてお迎えしてるわけです。昔からそう、自分でできることは自分でやる。最初は渋谷の東映だったんだけど、電球切れると天井裏をはっていって裏から変えてたの。梁から落ちたら天井が抜けちゃうから命懸けだよ!」
榎本さんが話し終わるとその場にいる番組スタッフ全員笑ってしまう。そんな軽やかなお話ぶりに、収録中終始笑いが絶えなかった。
シネマイーラの立ち上げ
榎本さんは18歳の頃から映写機を回していたそうで、19歳で東映に入社、それからは映画にまつわるすべてのお仕事を経験されてこられたそうだ。
「映写技師からボイラーマン、事務仕事もやって営業もやって。渋谷、新潟、浜松、新宿、横浜、それでまた浜松。全国の東映を渡り歩いてきました」
そんな榎本さんが東映を辞めてどうしてご自身で映画館を造ることになったんだろう。
「ここはもともと浜松東映だったんです。13年前に東映が撤退することになって、当時の岡田裕介社長にお願いして譲り受けました。会社は55歳で早期退職してね。浜松東映が閉館してから2カ月の間にお金集めて会社作って、椅子や内装も全部新しく変えて。結局使えたのは映写機だけだった。でもその映写機もすぐ、今度はデジタル化だっていうんでさ(笑)。いばらの道の13年! 大変でした」
浜松東映が閉館しても会社には残るという選択肢もあったわけで、当時「東映」ではなく「浜松」そして「新しい映画館」を選んだ榎本さんのお気持ちを想像してみる。町への愛着だろうか…。
シネマイーラを立ち上げるきっかけとなったのは、さかのぼること1988年、東映時代の劇場で榎本さんと市民有志の皆さんが始めたムーンライトシアターという上映会だったという。
「毎週木金土曜日の夜、東映としての営業が終わった後の時間に、今のシネマイーラにつながるミニシアター系作品を上映してたんです。タダみたいな安いお金で貸してたので会社の上からはよく怒られましたけど」
その活動は、浜松東映が閉館するまで20年間も続いたそうだ。
「毎回、みんなでディスカッションを重ねてやってました。配給会社は個人には作品を出さないから、東映の榎本が責任を取るということで僕が窓口になって。その時できたつながりはイーラになってからも活きましたね」
ムーンライトシアターとして20年間育ててきた種がシネマイーラとして実り、それから13年。一つ一つの積み重ねが今日につながっている。
榎本さんは映画館を飛び出して、次は浜松発の映画を作ろうと、自身がプロデューサーとなり、2013年には『楽隊のうさぎ』(中沢けい原作、鈴木卓爾監督)を完成させた。
「中学の吹奏楽部の話なんです。浜松の子どもたちをオーディションで集めて、廃校になる中学校を使って撮影してね。完成したら全国のミニシアターほぼ全部でかけてくれて。あれはうれしかったなぁ。うちで上映する時には出演してくれた子たち全員舞台に上げました。床が抜けるんじゃないかと心配だったけど(笑)。あれから8年たって、大学出たとか役者になったとか聞くとやっぱりうれしいですね」
33年前、ムーンライトシアターを始めた時に運営を手伝っていた当時の学生たちが、親になって今度は子連れで来てくれることも増えてきたという。いまスタッフとして働いている江間祐里さんも浜松ご出身。お母さまに連れられて中学生の頃から来ていたそうだ。

「この町にはもともと木下惠介監督から始まる映画の歴史があるんですよ。澤井信一郎監督、越川道夫監督、豊島圭介監督、俳優だったら鈴木砂羽ちゃん! みんな作品できると「エノさんこれかけて」「はいよ」ってなもんでね。映画の土壌があるんです。後で行きましょう、木下惠介記念館。映画監督の記念館なんて珍しいでしょう。歩いてすぐですから」
長年にわたり映画を通じて、浜松という「町」と「人」をしっかりと結び付けているご活動は、榎本さんの経験と行動力、温かなお人柄だからこそなせるものだとつくづく感じ入った。
音楽好きが集う映画館
館内に置かれた上映作品のチラシを見ると、やたらと音楽映画が多い。ビリー・ホリデイにコルトレーンにクラプトン、細野さんにドミンゴにデヴィッド・ボウイ。ジャンルも多彩だ。やはり楽器の町だからなのだろうか。
「ヤマハに河合にローランド、みんな本社は浜松にあるんです。楽器屋が多いのもこの町の特徴なので、音楽好きな人たちが大勢やって来る。音楽映画を見るならイーラでって思ってくれている人も多いので、うちの特権みたいな気はしますね。もともとこのビルを建てる時から映画館用に設計されているので、天井が他にないほど高くて音がいいんですよ。音楽以外でもシニアを中心に問題意識の高い方が多いのも特徴だと思います。歴史問題、環境問題、人権問題、かけると必ず観に来てくれる固定の層がいますね」

僕が観た『沈黙のレジスタンス~』にもたくさんのお客さんが入っていた。
「少しずつ戻ってきてくれてはいますが、とはいってもやはりコロナ禍です。昨年、何としても営業を続けるためにクラウドファンディングで支援をお願いしたら、本当にたくさんの人が応援してくださって…。あ、そうだ今日八太郎さんが来るっていうから、はい、これどうぞ!」
手渡されたのはフレンチブルドッグが小鳥を追う姿が描かれた素敵なトートバッグだった。
「これは『この世界の片隅に』('16)の片渕須直監督が、うちのクラウドファンディングの返礼品のために描き下ろしてくださったものなんです。門外不出の宝です。もう残りわずかなんだけど差し上げます!」
なんと、たいへん貴重なものをいただいてしまった。お心遣いに感謝して大切に使わせていただきます。
片渕監督とのつながりを教えていただく。
「当館来場・登壇数最多の監督です。『マイマイ新子と千年の魔法』('09)『この世界の片隅に』『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』('19)で舞台挨拶に来てくださったり、ほかにもシネマイーラ8周年記念イベントで行った「この世界の片隅に 公開前講座」など、シネマイーラを語るには欠かせない監督なんです」
「そうですか『マイマイ新子~』の頃からのお付き合いとは、さすがですね」
カメラが止まって番組プロデューサーの尾形さんが言うには『この世界の片隅に』以前のこの作品は、当初30数館という小規模での公開だったのだそうだ。
そろそろ開場時間だ。おじゃまにならないよう、しばらく外でスケッチをしながらお待ちし、榎本さんのご案内で散歩しながら木下惠介記念館に向かう。本当に気持ちの良い冬の青空だ。
「僕は(東京)神楽坂出身なんです。仕事で浜松に来たらこの町にすっかり惚れてしまって。結婚して家も建てて子育てもして、今は孫も3人。もうずっと浜松です。今日も暖かいでしょう。西から来る寒気が浜名湖で止まるんです。だから浜松は一年中春みたいなんですよ」
昼下がりの静かな町。ここまで話してくださったことを思い出しながら、日射しで白く輝く道を榎本さんと一緒に歩いていたら、最初に感じた「浜松」と「新しい映画館」を選ばれた理由が、すっきり腑に落ちた。

浜松を堪能する
木下惠介記念館は1930年、浜松銀行協会の集会所として建てられた建物で、現在は浜松市の文化財に指定されている。スタッフの戴周杰(タイ・シュウキ)さんが迎えてくださった。戴さんは北京電影学院で映画作りを学ぶ中、木下惠介監督の『楢山節考』('58)と出会い感銘を受け、それがきっかけで東京藝大大学院映像研究科に留学、今につながっているという。映画作家でありながらフィルムキュレーターとしてのお仕事もされている。日本語も大変お上手だ。
「浜松に来たばかりの頃は本当に知り合いが誰もいなくて大変だったんですが、いつも榎本さんが声を掛けてくださって。シネマイーラが私のよりどころでした(笑)」
記念館には木下惠介監督が実際に使っていた全49作品の台本やベネチアはじめ世界の映画賞のトロフィーなどが展示され、ホールにて毎月上映会も行なわれている。建物の設計は同じく浜松出身の中村與資平。他に現存する建物として静岡県庁、静岡市役所、静岡銀行本店、そして浜松営業部があると戴さんが教えてくれた。こりゃもう一日いて全部味わいたいなと心底思った。

「じゃあとんかつ食べに行こう! ほら戴くんも準備して!」榎本さんの号令で、ごひいきのとんかつ屋さん「とん兵衛」にご案内いただく。
「浜松に来たらうなぎって人多いんだけどね、僕はここのとんかつ! うちに来てくれた映画関係者はみんなここに連れてきます。今日はぜひカツ丼を食べてみてください」
あらかじめ予定を聞いていたので番組スタッフ全員、このために朝食を抜いている。僕らも本気である。とんかつを揚げる音、包丁で切る瞬間のサクッという音、卵を溶く音、そしてこのグツグツと煮込まれる時の甘い香り。今思い出してもよだれが出てくる。こんなにおいしいカツ丼を食べたことがない。肉にこだわるのはもちろん、秘密は3年寝かせたしょうゆなのだそうだ。シネマイーラ、木下惠介記念館、とん兵衛。東京から1時間半、このためだけに来る意味のある場所が三つも並んでいる。

ひと仕事終えたとん兵衛のご主人がお話くださる。
「この町でエノさんのこと知らない人なんていないよ!」
照れくさそうに笑って「貧乏が服着て歩いてるって言われてるんだ」と応える榎本さん。いえいえみんなに慕われていることがしっかり伝わります。最後の最後までその場の全員を笑わせてくださる榎本さんだった。
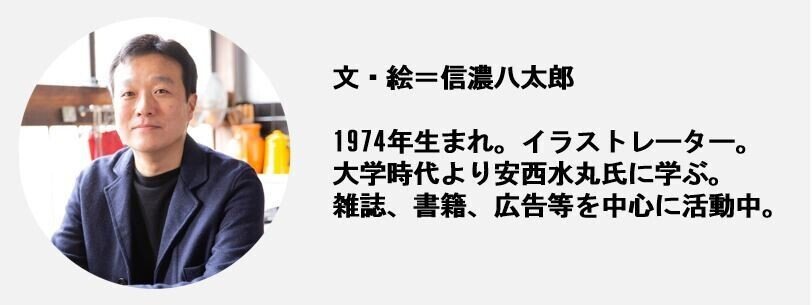
▼「W座を訪ねて~信濃八太郎が行く~」の今後の放送情報はこちら
▼「W座からの招待状」の今後のラインナップはこちら
▼WOWOW公式noteでは、皆さんの新しい発見や作品との出会いにつながる情報を発信しています。ぜひフォローしてみてください

