暴力には毅然と「NO」と言える輪を――映画から考えるロシアによるウクライナへの軍事侵攻
SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015年9月の国連サミットにて全会一致で採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す17の国際目標。地球上の「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」ことを誓っています。
フィクションであれ、ノンフィクションであれ、映画が持つ多様なテーマの中には、SDGsが掲げる目標と密接に関係するものも少なくありません。たとえ娯楽作品であっても、視点を少し変えてみるだけで、われわれは映画からさらに多くのことを学ぶことができるはず。フォトジャーナリストの安田菜津紀さんによる「観て、学ぶ。映画の中にあるSDGs」。映画をきっかけにSDGsを紹介していき、新たな映画体験を提案するエッセイです。
文=安田菜津紀 @NatsukiYasuda
今回取り上げるのは、第79回アカデミー賞で国際長編映画賞の前身となる外国語映画賞を受賞したドイツ映画『善き人のためのソナタ』('06)。
東西冷戦末期の東ドイツを生きる表現者たちには、常に権力者たちの監視の目がつきまとう。言論の自由が奪われる危機感は、現在のウクライナとロシアを巡る動きにも重なるものがある。SDGsの「目標16:平和と公正をすべての人に」「目標5:ジェンダー平等を実現しよう」を切り口に、この映画から今、世界で起きていることを考えます。


(SDGsが掲げる17の目標の中からピックアップ)
私自身はロシアに身を置いたことはない。それでも、次々と連行される人々の様子を、心震える思いで見ずにはいられない
あってはならないことが、また起きてしまった。2022年2月24日、ロシアがウクライナに軍事侵攻し、市民を犠牲にし続ける攻撃は、今なお続いている。故郷から引き剥がされ、国外へ逃れた人々は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)による3月29日の時点の調べで400万人を超えたとされる。
ウクライナでの空爆や砲撃が深刻であることはもちろん、ロシア側でもまた、気掛かりな動きがある。ロシアの政権関係者は、ウクライナを「攻撃」していることさえ認めようとしない。ロシア国営テレビの生放送中にスタッフが反戦を訴えたニュースはあったが、ほとんどのメディアはその姿勢を追認し、あらがおうとする報道機関は自ら幕を閉じざるを得なかった。こうした言論弾圧や報道への締め付けのように、人々から言葉を奪い、「知る権利」を阻む動きもまた、残忍な暴力だ。
権力側にとっては、人々が政治について発言しない、考えない状態を作り出したほうが好都合だ。だからこそこうして大衆を「空っぽ」の状態にしてしまおうとする。けれどもそう簡単に「空っぽ」にならないのもまた人間だ。だから今でも、ロシアの路上で声を上げ続ける人々がいるのだろう。
今私は、武力で脅かされることのない安全な場所から発信をしている。けれども、路上に繰り出したロシアの人々は違う。報道が規制され、「侵略」「戦争」といった言葉が禁じられる中、「戦争反対」を掲げただけで、幼い子どもたちまでもが警官たちに引きずられていく。それでもなお、沈黙ではない道を選んだ人々が、数千人という単位で拘束されている。
私自身はロシアに身を置いたことがない。肌感覚でこの国の恐怖や締め付けを感じ取ったことがない。それでも、次々と連行される彼らの様子を、心震える思いで見ずにはいられない。一体、どこからその勇気が湧いてくるのか。そして、同じ立場に立たされた時、私は、彼らになれるだろうか。
『善き人のためのソナタ』に学ぶ――政治や社会を考えることは、生きることそのものだ
40年近く前、ドイツ統一前の社会を描いた『善き人のためのソナタ』は、今まさにロシアで起きていることと重なる映画だ。時代はアメリカを中心とした西側諸国と、ソ連を中心とした東側諸国とで世界が引き裂かれていた冷戦の末期、その「東側」であった旧東ドイツが舞台となっている。ちなみにロシアのプーチン大統領も1985年頃、旧ソ連の秘密警察、KGBの一員として、東ドイツのドレスデンで任務に当たっていた。
東ドイツの国家保安省シュタージで、忠実に、そして冷徹に仕事をこなしてきたヴィースラー大尉(ウルリッヒ・ミューエ)は、ある時、反体制的な動きが疑われる劇作家ドライマン(セバスチャン・コッホ)と、ドライマンと同居している彼の恋人の舞台女優クリスタ(マルティナ・ゲデック)を監視することとなった。ドライマンの暮らすアパートにはくまなく盗聴器が仕掛けられ、家の中の暮らしは細部まで筒抜けとなった。けれども盗聴を通して、彼らの生活とともにある音楽、文学、思想に触れるごとに、ヴィースラーは揺れ動き、次第に彼らに共鳴していく。
ある時、腐敗した権力に毅然とした態度を取ったひとりの演出家が、自ら命を絶った。生涯を懸けたはずの職を追われた時、「息の根を断たれたも同然」と感じたのだろう。深い悲しみの中でドライマンが弾いたピアノの音に、しばしヴィースラーは自らの職務を忘れ聴き入った。それは、「この曲を本気で聴いた者は、悪人になれない」といわれる「善き人のためのソナタ」という曲だった。
ドライマンが「反体制」である証拠をつかめば、ヴィースラーには出世が約束されているはずだった。逆に彼らの動きを見過ごせば、ヴィースラー自身も無傷ではいられない。それでも、今ロシアの路上で「戦争反対」を叫ぶ人々のように、彼は迷い、躊躇しながらも、“善き人”としての行動を起こした。
SDGsの「目標16:平和と公正をすべての人に」の中には、汚職を排し、「国家及び国際的なレベルでの法の支配」を目指すことが掲げられている。力でねじ伏せるような恣意的な支配を終わらせなければならないと、この映画は今を生きる私たちに問い掛ける。
もう一つ考えたいのは、「目標5:ジェンダー平等を実現しよう」だ。監視国家の中で権力者の逆鱗に触れれば、自殺まで追い込まれた演出家のように、表現者としての道を断たれることは目に見えていた。その繊細なバランスの中で、ドライマンもクリスタも暗黒の時代を生き抜いてきた。けれどもある時、大臣の座にある男が、権力をちらつかせ、クリスタに近づいていく。彼女が直面したのは、男が誇示する「力」を利用した性暴力だった。権力者たちは彼女の命を、自身の支配欲を満たすための道具としてもてあそんだ。同じことが、今の世界でこれ以上、繰り返されてはならない。
硬直した社会に変化をもたらすことはたやすいことではない。けれどもこの映画で音楽や芸術が一人の心を動かしたような、小さな揺れ動きが寄せ集まった時、巨大な権力の盾に風穴があくのかもしれない。
声を伝えるのは報道機関だけの役割ではない。だからこそ今、表現者が、沈黙している場合ではない。私も時折「写真家がなぜ政治に発言するの?」と聞かれることがある。そして、似たような言葉がちまたにあふれている。「歌手がなぜ」「俳優がなぜ」、「スポーツ選手がなぜ」と。けれども政治や社会を考えることは、生きることそのものだ。タブー視する声にひるまず、暴力には毅然と「NO」と言える輪を、これからも広げていきたい。
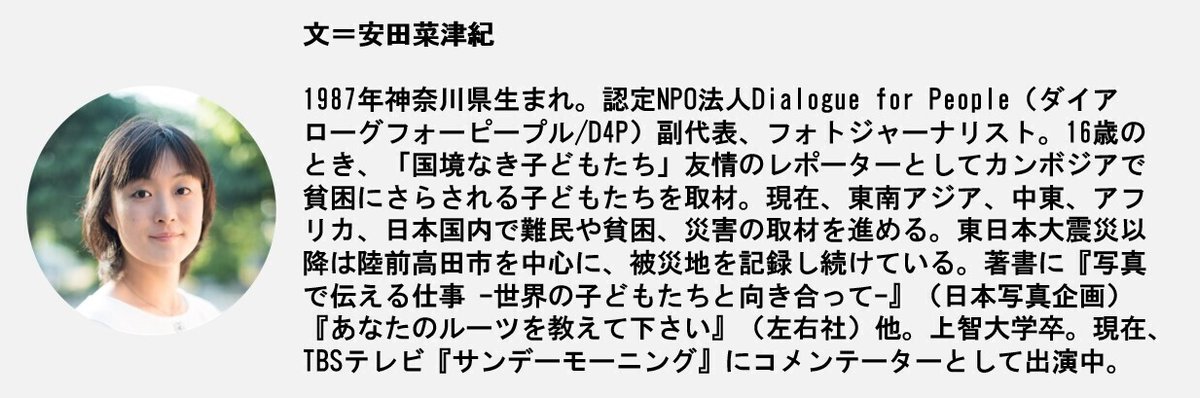

▼作品詳細はこちら
▼WOWOW公式noteでは、皆さんの新しい発見や作品との出会いにつながる情報を発信しています。ぜひフォローしてみてください。

