『ブロークバック・マウンテン』から『恋人たち』『his』まで――映画におけるLGBTQ+の今
マガジン「映画のはなし シネピック」では、映画に造詣の深い書き手による深掘りコラムをお届け。今回は、「『恋人たち』放送記念!監督 橋口亮輔」特集に合わせて、映画におけるLGBTQ+の描かれ方の変化を、ライター・編集者として活躍する、よしひろまさみちさんに聞きました。
文=よしひろまさみち @hannysroom
LGBTQ+をテーマにした映画は、世界的にみて2010年代から急増しているようにみえる。だが、これは劇中の彼らをステレオタイプにはめず、マジョリティであるストレート(便宜上この言葉を使いますが、正しくはヘテロセクシュアル)のキャラクターと同じように扱うようになった、という方が正しい。
というのも、アン・リー監督作『ブロークバック・マウンテン』(’05)よりも前に作られたLGBTQ+の映画といえば、主にゲイがコメディ・リリーフかストレートの敵として途中で消されたり、当事者が共感しがたい描かれ方をしていたりしたから。
それもこれも、1970年代から続く、性的マイノリティの人権運動が、2010年代に大きく変わったことが挙げられる。欧州で始まった同性婚やトランスジェンダーの人権向上の波が、アメリカ、アジアにも届き、世界中でLGBTQ+が正しく認知されるようになったおかげ、と言えるだろう。
だが、それもまだまだ足りていない。2020年、米国アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは、アカデミー作品賞に対して、多様性に配慮した条件を明文化したが、むしろ逆に「今まで明文化してなかったの!?」という驚きの方が大きい(ちなみに英国アカデミー賞は2016年から明文化している)。
とはいえ、ダイバーシティの尊重を推し進めてきたアメリカでも、正しい認知がなければ差別はなくならないことにようやく気付き、ダイバーシティをインクルージョン(=包含)とリプリゼンテーション(=表出)する方向に舵を切ったのは、大きな変革だ。
さて、これは日本を除いた話。悲しいかな、日本においてのLGBTQ+の理解は、欧米での1980年代くらいのステレオタイプで止まっている人が多いのが現実。学校や職場での噂話で「あいつ“コッチ”らしいよ」など、不用意な言葉がどれだけ当事者を傷つけているか。社会の中の異物として扱われる気持ちがいかなるものか、というところまで想像できれば、そんな言葉は出ないし、差別している側に明確な差別心がなかったりすることもたちが悪い。
2020年5月に発表された厚労省委託事業「職場におけるダイバーシティ推進事業」調査では、職場でカミングアウトしない理由として、LGBの32.1%、Tの32.9%が「接しづらくなるから」と回答している。それもこれも、なんでもかんでもステレオタイプにはめたがり、どこかにカテゴライズしないと気が済まない、という日本らしい考え方ゆえだろう。多人種による多様な社会であれば、人を何かに当てはめること自体がナンセンス。「十人十色」といういい言葉が日本語にはあるのに。
そんな文化的環境だからこそ、映画が持つ力を信じたくなる。それは橋口亮輔監督作品を観ていると、常に感じること。橋口監督は、長編映画デビューから27年にして長編は5作品と寡作で、どれもオリジナル脚本作品だが、そのどれもが日本映画の歴史において転機になる作品ばかりを作り出している映画作家。
デビュー作の『二十才の微熱』(’93)から一貫して、社会の片隅で孤立するマイノリティを描き続け、自身のセクシュアリティも公言した勇気ある監督だ。
その当時、1993年はメディアがこぞってゲイをとりあげたブーム期。とはいえ、コンサバティブな映画業界でゲイということを明らかにして仕事をするのは、今よりもずっと苦労が多かったことは想像に易い。しかも橋口監督の視点は、自身のセクシュアリティにとどまることはない。
性暴行で心に傷を持つ女子高生と、ゲイの噂に苦しむ男子高生の友情を描いた『渚のシンドバッド』(’95)、子どもを持ちたい女性とゲイカップルの関係を描く『ハッシュ!』(’01)、不器用にもひたむきに生きる人々の群像劇『恋人たち』(’15)……。どの作品も、社会さえ寛容であれば、自分らしく生き生きとした人生を送ることができるのに、現状を受け入れて静かに暮らす人々をとらえている。
このようなキャラクターを描くとなると、たとえばハリウッドであれば社会への不満をあからさまにぶつけたり、ときに説教くさくなってしまったりするもの。でも、これらはどれもそうではなく、実際にこういう人はどこかに必ずいる、と思わせる説得力がある。特に、自身のセクシュアリティでもあるゲイのキャラクターに関しては、特に手厚く、心の叫びをあぶりだす。
このような作品は、他ではあまり観られなかったタイプの作品ともいえるだろう。だが、近年、ちょっとずつではあるが、社会の中で声を出せずにいる者を描く映画は、日本でも増えつつある。特筆すべきは、LGBTQ+の扱われ方だ。橋口監督作のような、一歩引いた“やさしい視点”を継承するかのように、「特別ではない隣人」として描かれる機会も増えてきたのだ。
たとえば今泉力哉監督作『his』('20)のような作品。親権問題を抱えた男性とその元カレの家族愛にも似た関係を、彼らが対峙する偏見と差別を交えて描き出す。このような作品が出始めたことに、ようやく日本でも、と感嘆する。
他国と比べても、LGBTQ+のタレントがメディアに登場する機会が多い日本。だが、LGBTQ+の当事者はメディアの中だけの存在と思っている人も少なくはない。虚構の中の存在ではないし、誰の隣にもいることを、映画から学びとってもらいたい。
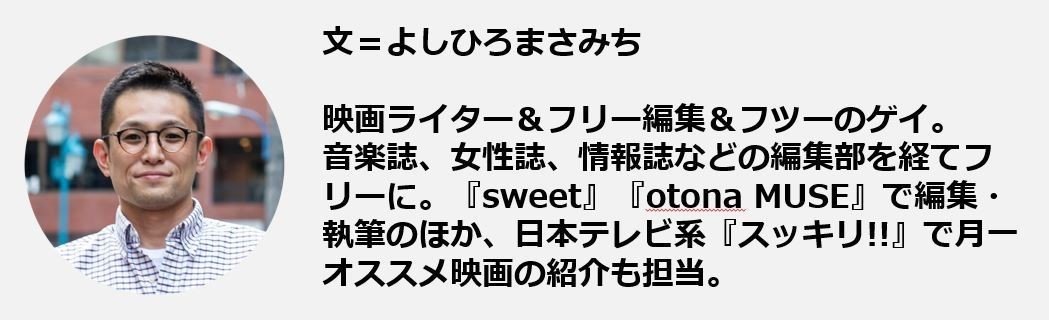
▼作品詳細はこちら

