ウクライナからの難民を取材するため訪れた地で、目の当たりにした「命の線引き」――『アンネ・フランクと旅する日記』が教えてくれること
SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015年9月の国連サミットにて全会一致で採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す17の国際目標。地球上の「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」ことを誓っています。
フィクションであれ、ノンフィクションであれ、映画が持つ多様なテーマの中には、SDGsが掲げる目標と密接に関係するものも少なくありません。たとえ娯楽作品であっても、視点を少し変えてみるだけで、われわれは映画からさらに多くのことを学ぶことができるはず。フォトジャーナリストの安田菜津紀さんによる「観て、学ぶ。映画の中にあるSDGs」。映画をきっかけにSDGsを紹介していき、新たな映画体験を提案するエッセイです。
文=安田菜津紀 @NatsukiYasuda
今回取り上げるのは、『戦場でワルツを』('08)のアリ・フォルマン監督がアニメーションで独自の世界観を描き出し、第34回ヨーロッパ映画賞の長編アニメ映画賞にノミネートされた映画『アンネ・フランクと旅する日記』('21)。
第2次世界大戦下のホロコーストによって15歳で命を落としたユダヤ人少女、アンネ(声:エミリー・キャリー)が綴った日記、「アンネの日記」。その日記に出てくる空想上の友達、キティー(声:ルビー・ストークス)が少女の姿で今の時代に現われるという、不思議な物語だ。日記が書かれた時代から70年以上の年月を飛び越えた今の社会は、キティーの目にどう映ったのか。SDGsの「目標11:住み続けられるまちづくりを」を軸に考えます。

(SDGsが掲げる17の目標の中からピックアップ)
ウクライナからの難民だけではない「命の線引き」
「ウクライナの人々と、これまでの中東からの移民・難民はもちろん違いますよ」
2022年5月、私はウクライナから避難した人々を取材するため、隣国ハンガリーで取材をしていた。ブダペストで出会った男性は、難民支援の在り方について問われ、こう答えた。私はてっきり、「人種や民族の間に不合理な違いを作り出して、命の線引きをしてはならない」といった趣旨のことを続けるのだと思っていた。なぜなら彼が、人道支援関係者だったからだ。ところが、だ。
「ハンガリーではオルバーン・ヴィクトル首相が、中東からの難民を受け入れたくないと訴えて、うまく支持を獲得してきました。政治家として手腕があると思いますよ。受け入れても治安が悪くなるし、違う文化圏から来ている人たちなのに、こっちの文化を受け入れようともしないでしょう」
その後、残念ながらここに書くこともはばかられるような差別発言が続いていった。私が中東取材を続けていること、現地にたくさんの友人がいることを伝えても、その論調は変わらず、彼は話し続けた。その日は一晩中、「人道」とはそもそも何なのかと考え込んでしまった。
実はその前に訪れていたポーランドでも、「命の線引き」を目の当たりにしたことがあった。ウクライナから避難する人々には素早く支援体制を整えたポーランドだったが、ベラルーシを経由して、ポーランドへと国境を越えてこようとする中東出身者らに対しては門戸を閉ざし、多くの人々が極寒の森をさまようことになった。
こうして人間らしい生活や安全を求め、実際に国境越えを試みた人々を取材したことがある。イラクから渡航し越境を試みた青年は、国境地帯で両国の警備隊から暴行を受け追い返されたと言い、「私たちはまるで、国と国との間にあるサッカーボールのようです……」と肩を落とした。シリアからEU圏内を目指そうとした男性は、「私たちのことを、未開の地から来た人間、あるいは動物だとでも思っているのでしょうか。私たちの国で戦争が起きることは、私たちの力ではどうにもならないことです」とうなだれた。
シリアで出会った別の男性は、真っすぐに私にこう語った。
「私たちの置かれた状況は、なぜウクライナほどの関心を集めないのでしょうか? 信じる宗教が違うからでしょうか? 私たちの目の色がヨーロッパの人々のそれとは違うからなのでしょうか?」
出会い、知ることにこそ、差別、偏見を解きほぐす大切な鍵があるのではないか
『アンネ・フランクと旅する日記』は、こうした「命の線引きの固定化」を問い、「人道とは何か」に立ち返るための映画だと私は思う。
この映画は、アンネが名前を付け、想像の中の友人に見立てた自身の日記の登場人物・キティーが、少女の姿で現代に現われる、という不思議な物語をアニメーションで描いている。この映画の大切なテーマは、最初のシーンから示されていたように思う。雷雨の中でも、アンネの博物館の開館を待ち、列を成す熱心な人々の姿がある。けれども彼らは、目の前でテントを吹き飛ばされ、凍えている難民の家族には、関心を寄せるそぶりがなかった。見えているはずなのに、見えていないように振る舞うのだ。
70年以上の月日を飛び越えてしまったキティーは、アンネの身に何が起きたのかを知らなかった。嘆き悲しみながらも、親友、アンネの最期までの足取りをたどることを望んだ。アンネの父、オットー・フランク(声:マイケル・マロニー)の本を片手に、ベルゲン・ベルゼン強制収容所を目指す。ユダヤ人としてどこにも「居場所」を得られなかったアンネの姿は、やがてキティーの中で、どの国からも受け入れられず、命の危険のある故郷に追い返されようとする難民の子どもたちと重なっていく。
「見えない」存在のように扱われている難民の人々の傍らに立ち、キティーは「ここにいる」と真っすぐに声を上げた。大切なのは、アンネの名前を建物や駅に刻むことではなく、アンネの日記からどんなメッセージを受け取るかではないのか、と訴えた。それは、誰かをただ象徴として扱い、思考することをやめていいのか、という強烈なメッセージだった。
SDGsの「目標11:住み続けられるまちづくりを」には、脆弱な立場に置かれた人々が追いやられることなく、安全な住まいを得るための地盤を確保することが掲げられている。キティーが出会った難民の子どもたちは、廃虚に暮らしていた。身を寄せたその国にただ、雨風をしのぐ場所があればいい、というわけではない。人間らしい暮らしが営める「居場所」を築く必要があるのだと、この映画は私たちに投げかける。
話をハンガリーで出会った男性のことに戻そう。彼は中東から来た移民・難民に対し、排他的な発言を繰り返したが、その語りのほとんどが、「ドイツなどでは治安が悪くなったらしい」「シリア難民はその国の文化を受け入れないらしい」という、ファクトに基づかない伝聞であり、直接そうした人々と語り合った様子はなかった。
逆に言えば、月並みな言い方ではあるものの、出会い、知ることにこそ、こうした差別、偏見を解きほぐす大切な鍵があるのではないかと改めて思う。映画は、日常生活を送る上ではなかなか出会うことのない他者と向き合う時間をくれるものだ。この『アンネ・フランクと旅する日記』も、社会の片隅に追いやられてしまった人々の、「ここにいるよ」という声に気付く、一つの契機になり得るかもしれない。
関心の格差、報道の格差は、支援の格差、命の格差につながっていく。その溝を常に埋めようと努め続けることこそ、「人道」なのではないだろうか。
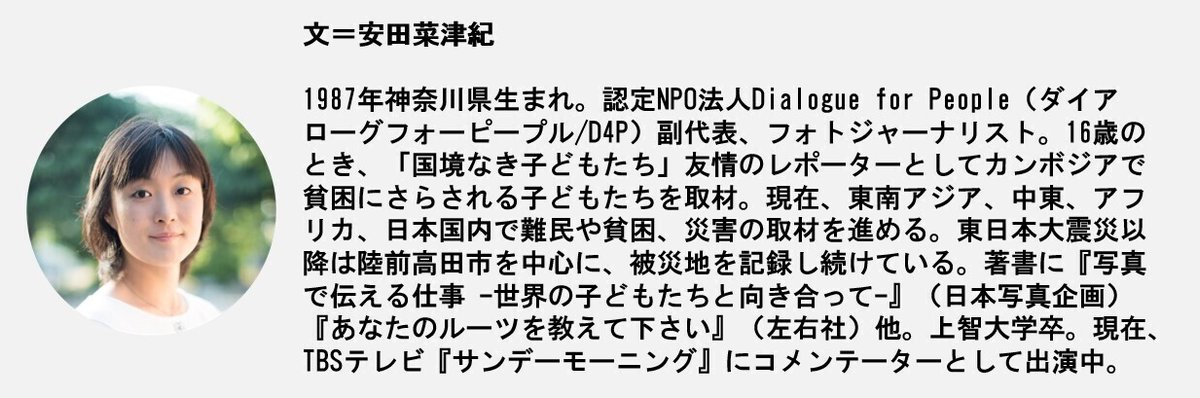

▼作品詳細はこちら
▼WOWOW公式noteでは、皆さんの新しい発見や作品との出会いにつながる情報を発信しています。ぜひフォローしてみてください。
クレジット:(C)ANNE FRANK FONDS BASEL, SWITZERLAND

