東日本大震災から10年、置き去りにしてはならないことは何か――1本の映画から考える
SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015年9月の国連サミットにて全会一致で採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す17の国際目標。地球上の「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」ことを誓っています。
フィクションであれ、ノンフィクションであれ、映画が持つ多様なテーマの中には、SDGsが掲げる目標と密接に関係するものも少なくありません。たとえ娯楽作品であっても、視点を少し変えてみるだけで、われわれは映画からさらに多くのことを学ぶことができるはず。
フォトジャーナリストの安田菜津紀さんによる連載「観て、学ぶ。映画の中にあるSDGs」。映画をきっかけにSDGsを紹介していき、新たな映画体験を提案するエッセイです。
文=安田菜津紀 @NatsukiYasuda
今回取り上げるのは、TV界で長年ドキュメンタリー畑を歩んできた久保田直が初めて劇映画の演出に挑んだ『家路』(’14)。
ある日突然、故郷を追われ、生業を奪われた家族の物語だ。東日本大震災による原発事故の影響で、仮設住宅での暮らしを余儀なくされ、農家としての誇りまで傷つけられ、苦悩しながらも自らの道を進もうとする姿が描き出されている。「人間らしく生きるとは何か」を問いながら、SDGsの「目標11:住み続けられるまちづくりを」についてもこの映画から考えてみたい。

(SDGsが掲げる17の目標の中からピックアップ)
どうして幼い子どもが6年近くがれきの中にいなければならなかったのか
窓からそっと、小学校の校舎の中をのぞき込む。地震の影響だろうか、教室の机の列はやや乱れているものの、辞書やノート、子どもたちの使っていた物がそのまま残されている。2011年3月11日は金曜日だった。この日の授業を終えた後、黒板は既に、翌週の月曜日、3月14日の日付に書き換えられていた。
福島県大熊町、熊町小学校の校舎には、あの日も「また来週」の声が当たり前のように響いていたのだろう。ところが午後2時46分、一帯は立っていられないほどの揺れに見舞われた。この学校の1年生だった木村汐凪(ゆうな)さんは当時、隣接する児童館におり、迎えに来た祖父の車で自宅に向かった後、行方が分からなくなった。汐凪さんが使っていた机の上には、「こびとづかん」が残され、壁に掲示された「がくしゅう係」の写真に、笑顔の汐凪さんが写っている。
この地を襲ったのは地震と大津波だけではなかった。東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機までが、大熊町の沿岸に立地している。翌12日には1号機が水素爆発、14日には3号機、15日には4号機と爆発が相次ぎ、町全域への立ち入りが制限された。汐凪さんの父、紀夫さんも、避難を余儀なくされ、家族の捜索を続けることができなくなってしまった。
その後、紀夫さんの妻の深雪さん、父の王太朗さんが遺体となって発見されたものの、汐凪さんの行方はつかめないままだった。紀夫さんは限られた一時帰宅の時間を使い、手作業で地道にがれきを掘り起こしながら、汐凪さんを捜し続けた。
環境省に依頼し、ようやく重機での捜索が開始されたのは2016年11月になってからだ。そこから1カ月もしないうちに、自宅跡地からほど近い場所で、泥だらけのマフラーから、小さな首の骨が見つかる。長女の舞雪さんは、汐凪さんとおそろいで持っていたそのマフラーのことを覚えていた。DNA鑑定の結果、その骨は間違いなく、汐凪さんのものだと分かった。
遺骨が見つかって間もない頃、私は紀夫さんが震災後に暮らしていた長野県白馬村の家を訪ねた。窓の外ではしんしんと雪が降り続け、止む気配がない。静かな部屋の一角に、その後見つかった顎の骨や歯などがそっと、置かれていた。「一部でも見つかったことを、喜ばなければ、と思うのですが、喜べない自分がいるんですよね」と、紀夫さんは悔しさをにじませる。「どうして汐凪が6年近くがれきの中にいなければならなかったのかっていうことを、どうしても考えてしまうんです」。
震災当日に捜索に入った地元の人の中には、紀夫さんの自宅周辺で「声を聴いた」という人もいる。父の王太朗さんは発災から49日後、その自宅の目の前の田んぼから発見された。もしかしたら王太朗さんも、そしてすぐ近くで発見された汐凪さんも、まだその時は生きていたのではないか。捜索を続けることができたら、助かっていたのではないか。紀夫さんはそんな思いを拭えずにいるという。そして、汐凪さんの大部分の遺骨はいまだ、見つかっていない。
大熊町は2014年12月、除染で出された大量の廃棄物を保管するための「中間貯蔵施設」受け入れを決めたが、紀夫さんは家族とつながる場所である自宅跡地を含め、自身の土地を売るつもりはなかった。建設にあたっての説明会で、「娘をまだ捜している」と紀夫さんが発言すると、国側の担当者は「行方不明の方がいるとは存じ上げなかった」と答えたという。そんな認識で計画を進めていたのか、という怒りが込み上げた。
汐凪さんが発見された場所には、コンクリート片を置いただけの簡素な慰霊碑がある。花を供えながら、紀夫さんがぽつりぽつりと語った。「この下にまだ汐凪がいるかもしれないんです。そんな場所が、中間貯蔵施設としてアスファルトで固められるなんて我慢できない。この土地も、これから造られる復興公園に加えてもらい、追悼のための施設を造れないだろうか」。
これだけの過酷な経験を経ながらも、紀夫さんは原発事故の原因を、津波や東京電力だけのせいだとは思っていないという。あの日まで無批判に電気を消費し続けていた自分自身への内省も込め、今はソーラーパネルなどから最小限の電気だけを使い、いつか大熊町に、農業や物づくりなどを通して、自給自足が可能な小さなコミュニティを築けないかと模索している。
そんな紀夫さんの言葉や生き方に触れると、人が「人間らしく生きる」とは何か、ということを考えさせられる。2014年6月、石原伸晃環境相(当時)は中間貯蔵施設建設に向けた地元との調整について「最後は金目でしょ」と発言し、批判を受けて後に撤回した。人の営みは果たして、「金目」だけで解決できるような簡単なものだろうか。亡くなった人々も含め大切な人とつながることができる場があり、自然と人間が同じ空間を分かち合えるような輪がそこにあることこそ、「人間らしく」あることなのであれば、紀夫さんが目指している未来に、そのヒントがあるのではないかと私は思う。
「住み続けられるまちづくり」は、他の街に犠牲を押しつけることで実現させていいものではないだろう
映画『家路』は、代々受け継いできた土地を守り生きてきた、ある農家の姿が描かれている。突然にその営みから切り離された兄、総一(内野聖陽)は、生気を失ったように、仮設住宅の片隅にただ座っているだけの日々を送っていた。母、登美子(田中裕子)は不慣れな生活の中で、徐々に体調を崩していく。
一方、長らく故郷を離れていた弟、次郎(松山ケンイチ)が、人知れず「警戒区域」の中の自宅に戻り、生活を始めていた。偶然通りかかった同級生に、東京の工場で、まるで機械の部品のように働いていたことがあったと次郎は漏らした。誰も暮らせなくなった集落の中でも、農作業に打ち込む次郎の姿はどこか生き生きとしていた。「体が覚えている」と慣れた手つきで種もみを選り分ける。一人でありながら、彼は孤独には見えなかった。農業を通して、命と対話し、その土地を、その技術を受け継いできた先祖や、家族と対話しているように見えた。
残念ながらSDGsの中に、「農業」というキーワードは「目標2:飢餓をゼロに」でしか盛り込まれていない。そこで、この映画から改めて考えたいのは、「目標11:住み続けられるまちづくりを」だ。この目標の中に「2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する」とあるが、それは危険なものを都市から遠ざけるだけで成しうるものだろうか。
例えば紀夫さんたちが暮らしていた大熊町では、事故から8年後の2019年4月10日から段階的に避難指示が解除されたものの、住民登録している約1万250人のうち、実際に大熊町に帰還して居住しているのは2021年2月1日時点で283人に留まっている。そして「帰還困難区域」では、いまだに除染作業などが続いている。廃棄物が運び込まれる中間貯蔵施設に至っては、約30年近く人が暮らせないことになる。
映画の中で次郎たちが暮らす場所も、その後、建設の候補地になっていたかもしれない。そうなれば、人の営みが戻ってくる、という意味での「復興」を、そもそも進めることができないのだ。「住み続けられるまちづくり」は、他の街に犠牲を押しつけることで実現させていいものではないだろう。この映画から、そんな構造的な問題にも目を向けていきたい。
間もなく東日本大震災から10年という月日が経つ。毎年3月になると、震災からの年数を「節目」として伝えようとする報道を目にする。けれども紀夫さんは、静かにこう語る。「自分にとっては毎日が、慰霊の日なんです」。置き去りにしてはならないことは何かを、改めて今、考えたい。
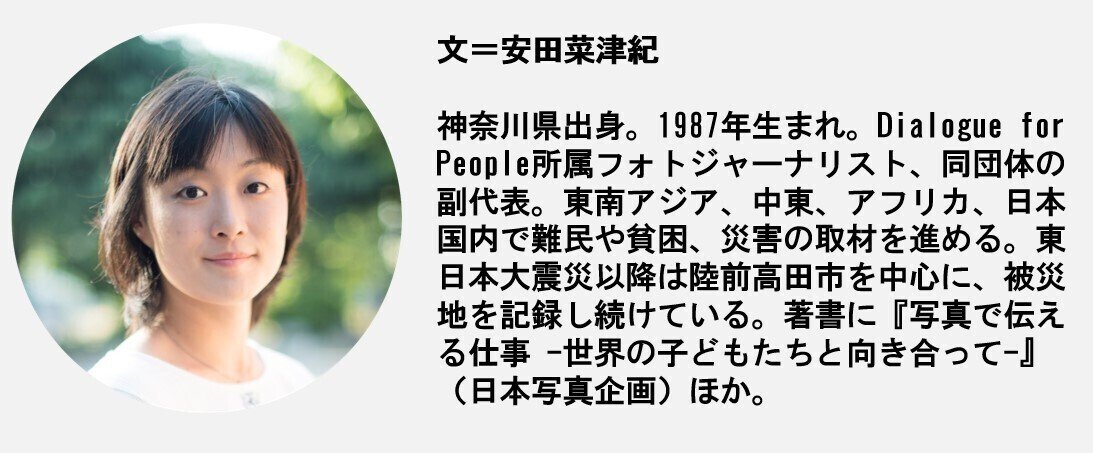

▼作品詳細はこちら

